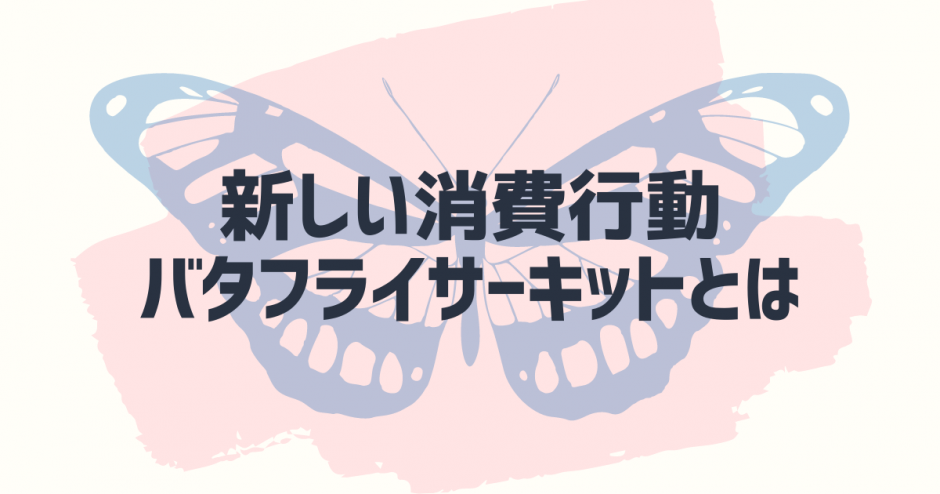SNSやスマートフォンの普及によって変化し続ける消費行動。今回はGoogleが提唱する新しい消費行動の『バタフライサーキット』とは何かを解説します。
>>効率よく学ぶならデジプロ!無料オンライン説明会はこちらから
目次
従来のマーケティングファネル
マーケティング戦略を設計する際に、様々なマーケティング従事者にAIDMAやAISASをはじめとするマーケティングファネル(パーチェスファネル)は好まれて活用されてきました。
AIDMAとは消費者の購買行動プロセスを段階的に説明したモデルの一つで、消費者は特定サービスを1. 認知して(Attention)2. 興味関心をいだき(Interest)3. 欲しい・使いたいと思い(Desire)4. 記憶し(Memory)5. 購買行動に移す(Action)ものだと定義しました。
AISASは2005年に電通が提唱したモデルで、インターネットの爆発的発達によりユーザーは『検索し、シェアする』という考えが組み込まれたものです。具体的には、消費者は特定サービスを1. 認知して(Attention)2. 興味関心をいだき(Interest)3. 検索して(Search)4. 購買行動に移し(Action)5. 共有する(Share)と定義したものです。
AIDMAもAISASも、いずれも『ユーザー行動はファネル状である』(逆流しない)という前提のもと、このモデルは提唱されており、マーケターにとってもそれは都合の良いことでした。
『ファネル状である』(逆流しない)ことが何故、マーケターにとって都合が良かったのかというと、マーケティング戦略が比較的簡単に立てやすくなるためです。
AISASモデルを例にすると『認知はあるが、興味・関心が弱い』のであれば、興味・関心を引き上げる施策を打てば、検索につながることになります。興味・関心を引き上げるためのテレビCMを実施した際は、SEO経由の流入をKPIにすればよいのです。
ファネルに囚われないパルス消費
2010年代に入るとスマートフォンが普及し、購買行動もデジタルシフトが加速していきました。Amazonやメルカリなど、インターネット上で商品を購入することが一般化され、TwitterやInstagram、Youtubeのユーザー増加によって商品情報のシェアが盛んに行われるようになりました。
それによって『衝動買い』のようなユーザーの瞬間的なニーズがインターネット上でも起こるようになり、企業はリスティング広告をはじめ様々なインターネット広告や、CRMを使ったアップセル、Web限定のキャンペーンなどを実施し、ユーザーの瞬間的なニーズ捉えようとデジタル専門のマーケティング組織を構築するなどしてマーケティング活動を手広にしていったのです。
2019年にGoogleはユーザーの瞬間的な『買いたい気持ち』を『パルス消費』と名付け、調査結果とともに新しい消費行動として発表しました。
この『パルス消費』は前述の『衝動買い』とは違い、インターネットの普及のおかげで、24時間いつでもどこでも買い物をすることができるため、普段購入している商品などにもこの『パルス消費』は発生するようです。
Youtubeで紹介されていた商品をその場でAmazonでポチる経験や、電車の中で暇だからマンガアプリ内で課金をする経験、雨が降っていたから実店舗ではなく公式サイトで購入した経験など、瞬間風速的に購入することを決断し、行動に移したことが一度はあるのではないでしょうか。
バタフライサーキットとは
上述の通り、インターネット・スマートフォンの普及により『パルス消費』という従来のマーケティングファネルでは説明ができない事象が、Googleの調査によって明るみになりました。
2020年、Googleはその『パルス消費』が起こるまでの情報探索へのモチベーションを『バタフライサーキット』と名付け、パルス消費と同様に調査結果とともに発表しました。
『バタフライサーキット』には大きく8つのモチベーションがあり、人々が選択肢を探るための「気晴らしさせて」「学ばせて」「みんなの教えて」「にんまりさせて」と、人々が選択肢を固める「納得させて」「解決させて」「心づもりさせて」「答え合わせさせて」と分類しました。
「さぐる」にあたる4つのモチベーションと、「かためる」にあたる4つのモチベーションを蝶のように行き来する、ということがバタフライサーキットの名前の由来です。
このバタフライサーキットは、従来のマーケティングファネル的な考え方は、現代における消費者の動向・ニーズには当てはまりづらいということを意味しており、この発表によってGoogleは、『パルス消費』とそれに紐づく8つのモチベーションに対して包括的にマーケティングアプローチしていく必要性を示したのです。
バタフライサーキットの状況下におけるマーケティングアプローチ
従来のマーケティングファネルにおいては『ユーザー行動は逆流しない』という前提があったため、キャンペーンのKPIやゴールを比較的簡単に設定することができました。
Actionを増やしたければコンバージョンをKPIに設定し、Attentionを増やしたければ認知調査の結果や、トータルリーチをKPIにすれば良かったのです。なぜならAttentionが増えれば、Interestも増え、Interestが増えればDesireも増える、といった具合にユーザー行動が進んでいくためです。
しかしバタフライサーキットの状況下において、このようなキャンペーン・ゴール設定は通用しなくなりました。
Attentionを増やしてもInterestが増えるとは限らない、Interestを増やしたら突然Actionも増えたなど、バタフライサーキットの状況下においてはマーケティングファネルに合致しないユーザー行動が多く発生するためです。
さてだいぶ前置きが長くなってしまいましたが、バタフライサーキットの状況下において、マーケティング担当者はどのようなアプローチを取るべきなのでしょうか?
Data Driven Attribution(DDA)を使ったフルファネル評価
1つは、こちらもGoogleが提唱するData Driven Attribution(以下DDA)を活用し、マーケティング評価を行うことです。
今までのマーケティングではコンバージョンがKPIの場合、最後の接点が評価対象になり、認知がKPIの場合、最初の接点が評価対象になることが殆どでした。
DDAは、ユーザーがコンバージョンに至るまでの全ての接点を評価対象とし、Googleが保有する膨大なデータや機械学習を用いて各接点を評価し、その貢献度毎に評価を割り振るというものです。
DDAを使うことで、バタフライサーキットという非連続的なユーザー行動の行き来をまんべんなく評価することができるようになります。
Googleが提供するDDAは大きく2つあり、Google広告上に評価対象を絞ったものと、各メディア・キャンペーンに対応したGoogle Analytics上で計測できるものに評価対象を広げたものがあります。
Google広告上のDDAを導入することで、指名ワードに比べてCPAが悪い傾向にあるBIGワードの再評価に役立てることができたり、一般的にリスティング広告では入札することが少ない『Knowクエリ』にもチャレンジする機会を見つけられるかもしれません。
またGoogle Analytics上のDDAでは、「ラスト評価だけするとSNSは良くないように見えるけど、DDAで評価をすると実は貢献度が高かった」などの各メディアの再評価や、デジタルマーケティング戦略の見直しする必要性の示唆を得ることができるかもしれません。
ファインドキャンペーンを使った「発見」を生み出すアプローチ
ファインドキャンペーンは、「ユーザーの新しい発見」をコンセプトに2020年ローンチしたGoogleの広告プロダクトの1つです。
Googleの調査によると、約59%のユーザーがYoutubeやGoogleディスカバーなどのGoogle上のプラットフォームで新しいお気に入りのブランドを発見した経験があるそうです。
ファインドキャンペーンはこの調査結果に基づき、Youtube・Googleディスカバー・Gmail面に、発見を促す広告を打ち出すことができる仕様です。
またファインドキャンペーンは、Googleの検索エンジンやYouTubeなどのGoogleサービスで、特定ののキーワードを検索したユーザーに対して配信ができる『カスタムオーディエンス』を使用して配信をすることが推奨されています。
このカスタムオーディエンスを使用することにより、検索、動画視聴(Youtube)、仕事や友人とのコミュニケーション(Gmail)、ニュース等の情報取得(Googleディスカバー)など、あらゆるユーザー行動の機会に対してマーケティングアプローチを仕掛けることができるようになります。
バタフライサーキットの中で、このように包括的なアプローチができる広告は、非常に有効な手段だと言えるのではないでしょうか。
バタフライサーキットは考え方の1つ
ここまでバタフライサーキットについて、かなりGoogleを持ち上げる形で解説してきましたが、最後に1マーケターとしての意見を述べたいと思います。
バタフライサーキットは具体的な調査によって明るみになった、紛れもない事実であることは確かです。今まで通りの評価手法や、マーケティングアプローチでは通用しなくなるということも確かです。
しかしバタフライサーキットは、あくまで「全体を俯瞰して見たら、そういう傾向があった」というだけであり、「すべてのビジネスにおいて、共通して言えることではない」ものでもあります。
Googleが情報探索行動を調査した業種は車・不動産・スキンケア・旅行・生命保険であり、それぞれの業種で約70%の消費者はバタフライサーキットを起こしていたとされています。逆を言えば30%は従来型の消費者行動をしており、さらに言えば他業種は「分からない」のです。
デジタルマーケティングの好事例は、全て再現性のあるものではありません。好事例を真似したくなる気持ちもわかりますが、その企業の置かれている状況によって課題が異なるため、そのまま真似ても上手く進まないケースが殆どです。
その観点を取り入れると、もしかしたら企業・サービスによっては従来型のマーケティングで攻めたほうが効果的、という可能性も捨てきれないのです。
そのためバタフライサーキットはあくまで「考え方の1つ」として念頭に置いておき、新しい戦略を立てるとき、マーケティング施策に行き詰まったときに、バタフライサーキットを思い出すくらいの方が健全でしょう。
特にこのような先進的なトピックは、手段と目的が入れ替わるきっかけになりがちです。
まずは自社のサービスにおいて、バタフライサーキットは起こり得るのか、起こり得ないのか、から考えてみるのが良いのではないでしょうか。