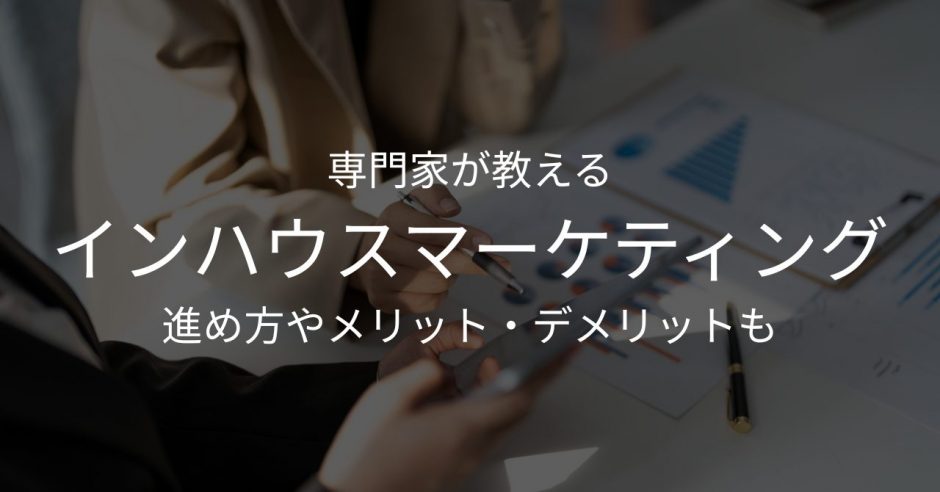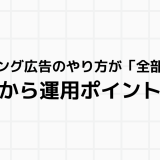マーケティング業務の「インハウス化」とは、広告運用やコンテンツ制作などのマーケティング活動を社内で実施することを指します。
企業が自社のマーケティング戦略を強化し、コスト削減やノウハウ蓄積、迅速な意思決定を実現するための重要な取り組みです。
しかし、多くの企業がインハウス化を進めるなかで、専門人材の確保が難しい、業務が属人化しやすい、社内に適切な教育体制が整っていないといった課題に直面しています。
マーケティングの知識やスキルが社内に根付かなければ、外部委託と変わらない状況になってしまい、期待した効果が得られないケースも少なくありません。
本記事では、インハウスマーケティングを成功させるための具体的な進め方を解説します。
インハウス化のメリット・デメリットを整理し、成功事例やおすすめの研修プログラムを紹介することで、自社に最適なマーケティング体制を構築するヒントをお伝えします。
目次
インハウスマーケティングとは
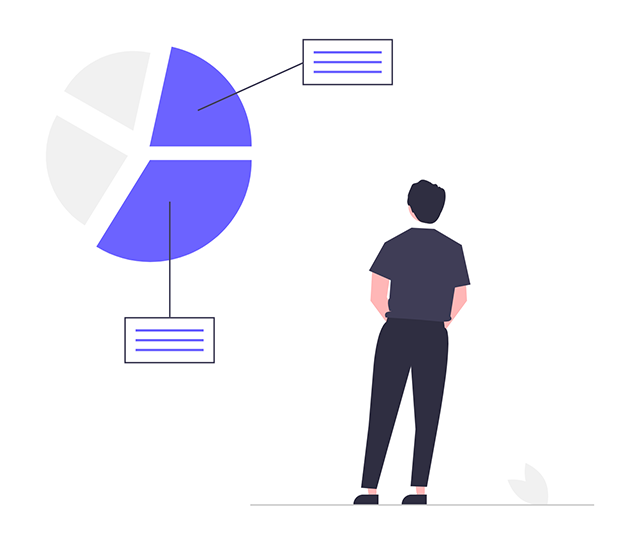
インハウスマーケティングとは、広告運用やSEO対策、SNS運用などのマーケティング業務を外部の代理店に委託せず、自社内で運用することを指します。
従来、これらの業務は専門の広告代理店やコンサルティング会社に依頼するのが一般的でしたが、近年ではコスト削減、社内ノウハウの蓄積、意思決定スピードの向上を目的に、インハウス化を進める企業が増えています。
インハウス化しやすいマーケティング領域
すべてのマーケティング業務を内製化するのは難しいですが、特にインハウス化しやすい領域として、以下3つが挙げられます。
1.デジタル広告運用
Google 広告やSNS広告などのデジタル広告運用は、比較的短期間のトレーニングで習得しやすいため、インハウス化が進みやすい分野です。
主要な広告プラットフォームは直感的に操作できる設計になっており、適切な研修を受けることで、自社のマーケティング担当者でも運用が可能になります。
2.SEO
BtoB分野のように、業界特有の専門用語やニッチなキーワードを活用するコンテンツ制作は、自社の知見を活かしやすいため、インハウス化するメリットがあります。
ただし、十分なリソースがない場合は、記事の構成案は自社で作成し、ライティングは外部の専門家に委託するといったハイブリッド型の運用も効果的です。
3.SNS運用
SNSはリアルタイムな投稿が求められるため、スピーディーな対応ができる社内担当者が運用を行うのが理想的です。
顧客からのコメントやメッセージへの対応は、ブランドイメージの向上にもつながるため、インハウス化のメリットが大きい領域です。
一方で、すべてのマーケティング業務を内製化できるわけではありません。
以下のような業務は専門知識やリソースが必要なため、代理店と協業するのが望ましいです。
1.オフライン広告(テレビCM・新聞広告など)
テレビCMや新聞広告は、出稿費用が高額であり、枠の確保やクリエイティブ制作などの専門的なノウハウが求められるため、基本的には広告代理店と連携するのが効果的です。
2.大規模サイトのSEO対策
1万ページ超のECサイトや求人サイトなど、データベース型の大規模サイトにおけるSEOは、高度なテクニカルSEOが求められるため、インハウス化は困難です。
このようなケースでは、SEOの専門家と協力しながら運用するのが得策です。
インハウスマーケティングのメリット

インハウスマーケティングは、単なるコスト削減が目的ではありません。
ノウハウの蓄積や迅速なPDCAなどさまざまなメリットをもたらします。
以下でそれぞれのメリットについて具体的に解説します。
1. コスト削減
マーケティング業務を外部に委託する場合、広告代理店や専門企業への手数料が発生します。
たとえば、広告運用を外注する際の一般的な手数料は、広告費の20%とされています。
仮に月間の広告費が200万円の場合、40万円が外注費としてかかる計算です。
スタートアップや中小企業にとって、この外注費は大きな負担となります。
限られた予算のなかで最大限の成果を出す必要がある企業にとっては、外部に支払うコストを削減し、より効果的な施策に資金を投じることが重要です。
マーケティング業務を内製化することで、外注費を削減し、そのぶんを広告費の増額や社内リソースの強化に回せるようになります。
2. ノウハウの蓄積
外注に依存する場合、マーケティングのノウハウや経験は代理店側に蓄積されるため、契約が終了すればその知見も失われるリスクがあります。
一方で、社内チームがマーケティングを担当すれば、スキルや知識が社内の資産として蓄積され、継続的な改善が可能になります。
たとえば、広告運用を社内で行うことで、「この商品は午前中の広告配信が効果的」「特定の地域ではクリック率が高い」といった示唆を得られるでしょう。
こうした知見をマーケティング部門だけでなく、営業や商品開発チームと共有すれば、より効果的な販売戦略や商品改善にも活用できます。
また、ナレッジ共有の仕組みを整えれば、個人の経験を企業全体の資産に昇華させ、組織全体のスキルアップにつなげることが可能です。
3. PDCAを迅速に回せる
デジタルマーケティングの世界では、PDCAサイクルをいかに速く回せるかが成果を左右します。
インハウスマーケティングの場合、代理店を介さず社内で施策を進められるため、意思決定から実行までのスピードが迅速化するのです。
よくあるケースが、広告内容の変更が迅速に行われないというもの。
外部代理店に広告の内容変更を依頼すると、確認作業や承認プロセスで数日かかることがあります。
そのため、「社内事情でクリエイティブの変更が必要になった」などへの対処が困難です。
しかし、インハウス化されていれば、担当者がその場でデータを分析し、「この広告文を修正したほうがよい」と判断して、即座に変更を加えられます。
このスピード感は特に競合が多い業界や、季節商戦のような短期間での勝負が求められる場面で強みになるでしょう。
4. コミュニケーションコストの削減
マーケティング業務を外部の代理店に委託する場合、社内チームと代理店の間でのやり取りが必要になり、その分の時間や手間が発生します。
施策の説明や意図の共有、成果報告の確認、修正依頼など、細かな調整が求められるため、これが「コミュニケーションコスト」として負担になるケースは少なくありません。
特に、代理店とのやり取りがメールや定例ミーティングを通じて行われる場合、ちょっとした修正依頼にも時間がかかり、迅速な対応が難しくなります。
さらに、情報の伝達ミスや認識のズレが生じると、意図した成果が得られず、追加の修正作業が発生するリスクもあります。
たとえば、広告のクリエイティブを変更する際に、依頼内容が正しく伝わらず、意図しないデザインになってしまうケースなどです。
一方で、インハウス化を進めれば、こうしたコミュニケーションコストを大幅に削減できます。
社内で情報共有が完結することで、意思疎通がスムーズになり、誤解や伝達ミスを最小限に抑えることが可能です。
また、マーケティング担当者が直接経営層や他部署と連携できるため、企業全体の戦略とマーケティング施策を統一しやすくなるというメリットもあります。
結果として、意思決定のスピードが向上し、より効果的なマーケティング施策を迅速に実行できる環境が整うわけです。
インハウスマーケティングのデメリット
インハウスマーケティングには多くのメリットがある一方で、企業規模やリソースによってはリスクや課題も発生します。
特に人材確保や属人化、初期コストといった問題は、インハウス化を進めるうえで慎重に考慮する必要があります。
ここでは、インハウスマーケティングのデメリットについて見ていきましょう。
1. 専門人材の確保
インハウスマーケティングの実施には、広告運用やSEO、データ分析などの専門スキルを持つ人材が必要です。
しかし、近年のデジタルマーケティング分野では人材不足が顕著で、高度なスキルを持つ人材の採用競争が激しくなっています。
さらに、採用した人材を長期的に活用するためには、定期的なスキルアップ研修や最新トレンドを学べる環境の整備が不可欠です。
SEO分野では、Googleのアルゴリズムが定期的に更新されるため、最新情報を常に追い続ける必要があります。
こうした専門知識を持つ人材を維持・育成するには、時間とコストがかかるのが現状です。
2. 属人化リスク
インハウスマーケティングでは、特定の担当者に業務が集中する「属人化」のリスクが発生します。
1人の社員がすべての広告運用からSEOまで行っている場合、その社員が急に休職したり退職したりすると、業務がストップしてしまう恐れがあります。
属人化を防ぐには、業務の分担や標準化が必要です。
作業マニュアルの作成やチーム内での定期的な勉強会の実施、ナレッジ共有ツールによる施策の進捗状況や成果データの記録・共有などを活用し、業務の引き継ぎをスムーズに行える体制を構築しましょう。
3. 最新情報の不足
代理店や外部パートナーは、SEOやWeb広告などのプロとして活動しているため、業界トレンドや最新情報を把握しています。
たとえば、Google 広告の認定パートナーの場合は、Googleより最新情報の共有や新機能のβ版を一足先に提供されるため、最新トレンドに基づいた運用が可能です。
一方でインハウス化した場合、社内チームだけで情報を収集・分析しなければならず、時には市場の変化に対応しきれないリスクがあります。
そのため、社員がセミナーや勉強会への参加、最新ツールやトレンドを学ぶ時間の確保が求められます。
4. 初期コストがかかる
インハウスマーケティングを始める際には、以下のような初期コストがかかります。
- ツール導入費用:SEOツールや広告運用ツール、データ分析ツール
- 人材育成コスト:社員がマーケティングを学ぶための研修プログラムやオンラインコースへの参加費
- 採用コスト:デジタルマーケティングの専門人材を採用する際のコスト
さらに、初期段階では社員がスキルを習得するまでの時間も必要です。
この間、施策の成果が一時的に低下する可能性もあります。
ただし、これらの初期コストは、長期的な視点で見ると十分回収可能であり、計画的に進めることが重要です。
インハウスマーケティングに失敗しないポイント

インハウスマーケティングの成功には、戦略的な進め方や段階的なアプローチ、そしてチーム作りが欠かせません。
ここでは、失敗を防ぎながら成果を上げるための具体的なポイントを解説します。
1. 内製化すべき業務を見極める
すべてのマーケティング業務を内製化するのは現実的ではありません。
限られたリソースのなかで最大の成果を上げるためには、インハウス化に適した業務と、外部委託が望ましい業務を明確に区別することが重要です。
まずは、SNS運用・広告運用・メールマーケティングなど、比較的負担が少なく、短期間で成果を出しやすい業務のインハウス化に取り組むのが効果的です。
特に広告運用は、適切な知識を身につければ自社で運用可能であり、短期間で成果を可視化できるため、インハウスマーケティングの成功体験を積むには最適な領域です。
さらに、成功事例を経営陣と共有することで、組織全体のインハウス化への理解と協力を得ることにもつながります。
一方で、テクニカルSEOや高度なクリエイティブ制作など、専門性が高く、社内での習得に時間がかかる業務は外部の専門家に委託するのが賢明です。
たとえばSEOでは、キーワード選定やデータ分析は社内で行うべきですが、記事執筆などのコンテンツ制作は経験豊富なライターに外注することで、社内のリソースをより戦略的な業務に集中できます。
このように、「何をインハウス化し、何を外注するか」の判断を明確にすることが、成功するインハウスマーケティングの第一歩となります。
2. 段階的に進める
インハウス化を急ぎすぎると、リソース不足やチームの疲弊につながり、成果が伴わない場合があります。
そこで、一部の業務から試験的に内製化を始め、徐々に範囲を広げる段階的なアプローチをおすすめします。
最初にインハウス化の対象となる業務を限定し、スモールプロジェクトから開始しましょう。
先にもお伝えしましたが、早い段階で成功体験を得るという意味でも、Web広告運用がおすすめです。
スモールプロジェクトを開始したら、成果を検証し、改善点を明確にします。
その後、ほかの業務やチャネルにも徐々にインハウス化を拡大します。
段階的なアプローチをとることで、負担を最小限におさえながら、インハウス化を進められるでしょう。
3. 人材育成とチーム作り
インハウスマーケティングの成功を左右するのは、最終的に「人材」です。
理想は、高度なスキルを持つ人材を採用することですが、それが難しい場合は、既存の社員を育成する仕組みを整える必要があります。
効果的なのが、体系的なマーケティング研修の活用です。
マーケティングの知識は自己学習でも習得可能ですが、実務に追われて学習時間を確保するのは簡単ではありません。
研修を受講することで、強制的に学習時間を確保し、短期間で実践的な知識とスキルを習得できます。
たとえば、オンライン講座やワークショップ形式の研修を活用すれば、実務に直結するアウトプットを伴う学習が可能です。
また、インハウス化を進める際は、チーム内での役割分担を明確にし、業務の属人化を防ぐ工夫が求められます。
広告運用、コンテンツ制作、データ分析など、担当者ごとに専門領域を決めるのが理想ですが、リソース不足により一人で複数の業務を担うケースも少なくありません。
その場合は、必要に応じて外部パートナーの協力を依頼するのが望ましいです。
4. 社内教育とナレッジ共有の仕組み作り
継続的な学習機会を設け、チーム全体でナレッジを共有できる環境を構築することで、マーケティングのインハウス化をよりスムーズに進められます。
そのために、まず定期的な学習機会の確保が不可欠です。
外部セミナーやウェビナーを活用し、最新のマーケティングトレンドや成功事例を学ぶ機会を設けて、社員の知識を常にアップデートしましょう。
また、ナレッジを組織内で共有する仕組みも重要です。
専用のナレッジ共有ツールを導入し、社員が学んだことや成功や失敗の事例を記録・蓄積できる環境を整えましょう。
プロジェクトごとの振り返りを定期的に行い、施策の成果や課題をチーム全体で共有することで、個人の学びを組織の資産へと昇華できます。
5. 外部リソースとの連携
内製化と外注の「ハイブリッド型」を取り入れることで、リスクを抑えつつ柔軟な体制を構築できます。
具体的には、広告運用は内製化しつつ、クリエイティブ制作は引き続き代理店に依頼するといった形が考えられます。
また、社内で対応できない部分については、専門家を短期的に雇用する「スポット契約」も有効です。
デジプロ受講生のインハウスマーケティング成功事例
インハウスマーケティングを成功に導くためには、適切なノウハウやツールの活用が欠かせません。
デジプロを受講した企業の実例は、インハウスマーケティングが企業に成果を示す指標となります。
以下に、具体的な事例をご紹介します。
事例1:Web広告のコンバージョン数が3倍に!

株式会社清長は、物流サービスを提供する企業で、Webマーケティングの強化を目指して、初の専任担当者として山口さんを採用しました。
山口さんは、前職でWeb集客に携わった経験を持ちながらも、広告運用に関しては未経験でした。
同社は、Webマーケティングの内製化を推進するため、デジプロの研修プログラムを導入します。
デジプロの研修では、現役のマーケターが講師を務め、受講者のレベルや企業の状況に応じたカスタマイズした指導を展開しました。
山口さんは、講義を通じて広告運用の基礎から実践的なスキルまでを習得し、特に広告代理店とのコミュニケーションにおいて、対等に議論できる知識を身につけたと振り返っています。
研修後、山口さんは過去の広告レポートを分析し、長期間にわたり数値の大きな変化がないことを発見しました。
この気づきを基に、広告代理店との関係を見直し、運用の改善に取り組みました。
その結果、同社の提供する「ロジモプロ」というサービスにおいて、コンバージョン数が従来の3倍に増加し、実測値も1.4倍に向上したそうです。
この成功事例の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
事例2:広告運用の深い理解で、代理店との連携を強化

株式会社イルグルムの馬場さんは、広告運用の経験がないなか、転職を成功させ、運用型広告レポート自動作成ツール「アドレポ」のセールスを担当されていました。
業務を通じて広告代理店と接するなかで、広告運用者の思考や業務フローを深く理解する必要性を感じ、デジプロの研修を受講されました。
デジプロの研修では、プロのWebマーケターから直接指導を受け、広告の入稿方法やプランニングなど、広告運用者の思考を一通り体験できます。
これにより、顧客からの具体的な提案にもその場で対応できるようになり、コミュニケーションの質とスピードが向上したそうです。
さらに、広告代理店に委託している自社広告の発注指示も具体的に出せるようになり、運用の成果も向上しています。
このように、デジプロの研修を通じて、広告運用の知識を深めることで、業務の効率化や事業のスケールアップに成功しています。
この成功事例の詳細は、以下記事でご確認 ください。
インハウスマーケティング化にはデジプロの研修がおすすめ!

インハウスマーケティングを成功させるには、実践的なスキルや知識を社員が習得することが重要です。
しかし、マーケティング業務をゼロから学ぶのは時間もコストもかかります。
そこで役立つのが、現役マーケターが指導する実践型の研修プログラム「デジプロ」です。
以下では、デジプロが企業のマーケティング研修に選ばれる理由をご紹介します。
1. 実務に直結したカリキュラム
デジプロのカリキュラムは、理論だけでなく、現場で即戦力となる実践的なスキル習得を重視しています。
たとえば、Google 広告やMeta広告の具体的な運用方法に加え、広告効果を最大化するデータ分析・活用術も学べるため、単なる知識習得にとどまらず、実務で成果を出せるスキルが身につきます。
さらに、実際の広告アカウントを用いた演習を行い、受講後すぐに自社のマーケティング業務に応用できるのも大きな特徴です。
机上の学習ではなく、実際の運用環境で試行錯誤しながら学べるため、「知っている」だけでなく「できる」レベルに引き上げることが可能になります。
2. 企業のニーズに合わせたカスタマイズ
企業ごとに抱える課題や目指すゴールは異なるため、画一的な研修では十分な成果が得られません。
デジプロでは、企業のニーズに応じて研修内容を柔軟にカスタマイズするため、特定の業務や目標に応じたスキル習得が可能です。
自社の実情に即した研修を受けることで、受講後すぐに実務へ活かしやすく、より実効性の高いスキル習得を行えます。
3. 持続可能なサポート体制
デジプロは、研修終了後も実務で成果を出し続けられるよう、充実したアフターフォローを提供しています。
研修を受けても、いざ実務に取り組むと「学んだ知識をどう応用すればいいのか」「想定外の課題に直面した」といった悩みが生じることがあります。
デジプロでは、受講後も継続的に相談できる仕組みを整えており、実務でつまずいた際に適切なサポートを受けられるため、スキルを定着させやすいのが特徴です。
また、受講生同士のネットワークを活用した情報交換の場も提供しており、学習後もマーケティングトレンドや成功事例を共有しながら、スキルの向上を図れます。
これにより、研修が一過性の学習で終わるのではなく、実践的な知識として根付き、長期的な成果につながる体制を構築できるのです。
助成金の活用やお客様の声など、デジプロの法人向け資料は以下より、無料でダウンロード可能!