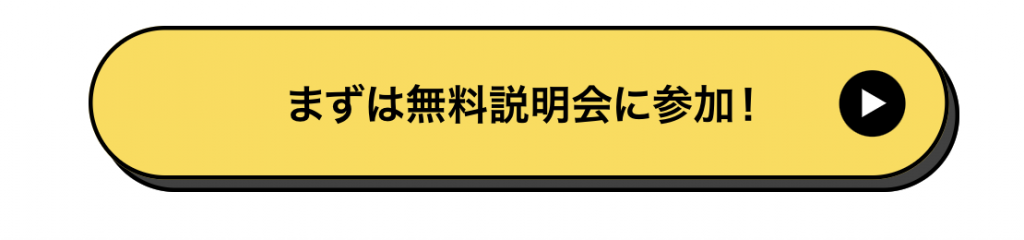デジタルテクノロジーの発展により、ネット社会になりつつある現代では、Web広告の需要が増加傾向にあります。
そのため、Webマーケティング施策のなかでも比較的短期間で集客効果を得られる「Web広告運用」の導入を検討する企業も多いのではないでしょうか。
そもそもWeb広告とは、Web上に配信される広告全般を指し、細かなターゲティングと素早い効果測定による顧客分析が特徴です。
予算が限られている場合でも、Web広告を活用することで費用対効果の高い広告運用を目指せます。
Web広告を効果的に運用するには、「自社に合うWeb広告を見極める」ことが重要なカギです。
本記事を読めば、Web広告プロダクトそれぞれの特性を理解した上で、自社に最適なWeb広告の選定が可能になります。
効果的にWeb広告を運用したいのであれば、ぜひ最後までご覧ください。
>>効率よく学ぶならデジプロ!無料オンライン説明会はこちらから
目次
主要なWeb広告は12種類

Web広告運用において、自社商品やサービスに合った広告プロダクトを選定するのは非常に重要な要素です。
本見出しでは、近年の主要なWeb広告プロダクトである以下12種類をピックアップし、メリットやデメリット・課金方式について詳しく解説します。
- 純広告
- リスティング広告
- ディスプレイ広告
- リターゲティング広告
- 記事広告
- アフィリエイト広告
- 動画広告
- メール広告
- 音声広告
- リワード広告
- SNS広告
- インフルエンサー広告
ターゲットや予算などをイメージしながら、自社に合う広告プロダクトを探してみてください。
純広告
| メリット | ・アクセス数の多いWebサイトに掲載できるため、認知拡大につなげられる ・商品やサービスのブランディングに活用できる ・一度出稿すると運用の手間がかからない |
| デメリット | ・出稿費用が高額になる ・詳細なターゲティングができない ・掲載期間中は広告内容の差し替えができない |
| 課金方式 | ・期間保証方式 ・インプレッション保証方式 ・インプレッション課金方式 ・クリック保証方式 ・クリック課金方式 ・配信課金方式 ・成果報酬方式 |
| ターゲット | 潜在層 |
純広告とは、特定のWebサイトに設けられた広告枠を購入し、期間限定で広告を掲載できるWeb広告のことです。
例えば、Yahoo!のトップページの右上に掲載されている広告は、皆さんもイメージしやすいのではないでしょうか。
ほかにも、アクセス数が多いWebメディアに広告掲載を依頼する形式の純広告もあり、課金方式もさまざまです。
純広告は多くのユーザーへの認知につなげられるため、自社の信頼性向上やブランディングにも期待できます。
Web広告の多くは出稿後の運用作業が重要ですが、純広告では一度出稿すると調整作業が必要ありません。
そのため、運用管理のコストがかからないというメリットもあります。
しかし、広告を出稿する料金が高額になる点はデメリットです。
「試しに出稿して様子をみてみる」といった方法は難しく、出稿後に修正ができないため、十分に準備した上で出稿する必要があります。
リスティング広告
| メリット | ・見込み客にアプローチできる ・費用対効果の高い広告運用が期待できる ・検索結果に上位表示できるため、即効性がある ・低予算で始められる |
| デメリット | ・潜在層にはアプローチできない ・キーワードによって広告単価が高くなる ・「広告」と表示されるため、意図的に避けられる場合もある |
| 課金方式 | クリック課金方式 |
| ターゲット | 顕在層 |
リスティング広告(検索連動型広告)は、ユーザーの検索キーワードに応じて、GoogleやYahoo!といった検索エンジン上に表示されるWeb広告です。
検索ユーザーは自身の知りたいことを検索するので、すでに興味関心を持っているユーザーに絞って広告を表示できます。
一方、そのほかのユーザーには届かないため、認知拡大や潜在層へのアプローチはできません。
料金体系はクリック課金方式で、ユーザーがクリックしてページにアクセスすることで初めて費用が発生します。
広告が表示されただけでは料金が発生しないため、キーワードの競合性にもよりますが、費用対効果の高いWeb広告といえます。
ただし、競合の多いキーワードでは、1クリックあたりの単価が高くなる可能性があるので、注意が必要です。
ディスプレイ広告
| メリット | ・潜在顧客へのアプローチができる ・ビジュアルを使った広告で目につきやすい ・1回あたりのクリック単価が安い |
| デメリット | ・配信先の広告枠を選べないため、ターゲット以外のユーザーにも表示される ・コンバージョン率が低い傾向にある ・問題点を発見するのが難しい |
| 課金方式 | ・クリック課金方式 ・コンバージョン課金方式 ・インプレッション課金方式 |
| ターゲット | 潜在層 |
ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリなどの媒体の広告枠に表示される広告全般のことです。
一度に複数のWebサイト・アプリに広告を表示できるため、多くのユーザーに自社商品やサービスの認知を促せるのがメリットです。
また、画像や動画などのビジュアルをメインとした広告なので、ユーザーの目につきやすく、クリエイティブな面で興味を惹けるとクリック率も高まります。
一方、デメリットは配信先の広告枠を選べないため、ターゲットではないユーザーにも表示される可能性が高いことです。
ターゲットを狙った配信ができないため、コンバージョン率は低くなり、効率の悪い広告運用になる傾向にあります。
さらにディスプレイ広告では、改善するにあたってビジュアルや広告の掲載サイズなど、さまざまな要素を考慮する必要があります。
そのため、ほかのWeb広告と比較するとPDCAを回すのに一定の時間がかかるでしょう。
リターゲティング広告
| メリット | ・配信ターゲットを細かく絞り込める ・コンバージョン率が高い ・費用対効果が高い |
| デメリット | ・ユーザーに「しつこい」と不快感を与える可能性がある ・潜在層や新規層の取り込みには不向き ・配信するにはユーザー情報を収集する必要がある |
| 課金方式 | ・クリック課金方式 ・インプレッション課金方式 |
| ターゲット | 顕在層 |
リターゲティング広告とは、過去に自社サイトのページにアクセスしたユーザーに対して再度表示するWeb広告のことです。
インターネットやSNSを利用しているとき、同じ広告が何度も表示された経験はありませんか?
これは、過去に閲覧した自社のサイトに対して再び興味関心を持ってもらうために、広告主が表示しているリターゲティング広告によるものです。
過去に自社サイトへアクセスしたユーザーは、商品やサービスの購入を検討した経験や、情報に関心があった経験があり、顕在ニーズが高い傾向にあります。
リターゲティング広告は顕在ユーザーに絞って広告配信ができるため、ほかのWeb広告と比較してコンバージョン率が高いのがメリットです。
一方のデメリットは、すでに興味関心が薄れたユーザーにも表示されるため、「しつこい」「追いかけられている」などの印象を与える可能性があります。
このような事態を防ぐためにも、適切な配信回数を設定するなど、ユーザーのストレスになりにくい工夫が必要不可欠といえるでしょう。
また、出稿するには広告媒体ごとに決められたリストを作成する必要があります。
例えば、Googleであれば過去30日に100ユーザー以上のリストが必要となり、設定数を下回ると配信できません。
そのため、配信するまで手間と時間がかかります。
記事広告
| メリット | ・高い信頼性がある ・自社の権威性やブランド力の強化にもつながる ・自然に閲覧してもらえる |
| デメリット | ・掲載するまでに時間がかかる ・掲載費用が高額になる傾向にある ・記事作成に手間がかかる |
| 課金方式 | 記事単位で費用が異なる |
| ターゲット | 顕在層と潜在層 |
記事広告とは、Webメディアに依頼して、自社商品やサービスを紹介してもらうWeb広告のことです。
「タイアップ広告」「PR広告」とも呼ばれます。
広告主ではなく、Webメディア側が第三者目線で記事を作成するため、ユーザーからの信頼を得やすいのが特徴です。
PV数の多いニュースサイトやメディアに掲載してもらえれば、自社の権威性やブランド力の認知にもつながります。
しかし、記事広告はほかのWeb広告と比較すると掲載費用が高い傾向にあり、情報を共有するために何度も打ち合わせを行うので、手間がかかります。
実績のある有名なメディアの場合には、すでに多くの企業が依頼しているケースが多く、掲載するまで時間がかかるため、注意しましょう。
アフィリエイト広告
| メリット | ・集客の手間が省ける ・広告内容や報酬によっては、多くのアフィリエイターから掲載してもらえる ・費用対効果が高い |
| デメリット | ・アフィリエイターによって成果に差が出る ・アフィリエイターによっては、商品やサービスのイメージダウンにつながる ・初期費用、月額費用、利用手数料がかかる |
| 課金方式 | 決められたコンバージョンの達成率によって異なる |
| ターゲット | 顕在層と潜在層 |
アフィリエイト広告とは、ブログやSNSを運営するアフィリエイターに、自社の商品やサービスを宣伝してもらう成果報酬型のWeb広告のことです。
広告が閲覧されたりクリックされたりしただけでは料金は発生せず、購入や資料請求といった商材ごとに決められたコンバージョンを達成した時点で報酬が発生します。
報酬は広告主側で自由に設定できるため、費用対効果の高い広告運用が可能です。
しかし、広告主側はアフィリエイターを選べないため、必ずしも閲覧ユーザーの多いWebサイトに掲載してもらえるとは限りません。
したがって、アフィリエイターの利益も考慮した上で、適切な報酬額を設定する工夫が必要です。
また、アフィリエイターによっては自社が意図しない過激な表現を用いることもあります。
その結果、自社のイメージが悪くなる可能性があるので、定期的に掲載先のチェックを行いましょう。
アフィリエイト広告は、成果報酬とは別に初期費用や月額費用、利用手数料などの固定費がかかるため、いくつかのASPを比較検討した上で利用することが重要です。
動画広告
| メリット | ・広告にストーリー性を持たせられる ・印象に残りやすい ・広告内容によっては興味関心の薄いユーザーにも閲覧してもらえる |
| デメリット | ・広告作成に時間がかかる ・広告制作費用が高くなる傾向にある ・コンテンツの質が悪いとユーザーがストレスを感じる |
| 課金方式 | ・動画を再生されるごとに発生する課金方式 ・インプレッション課金方式 ・クリック課金方式 |
| ターゲット | 顕在層と潜在層 |
動画広告は、WebサイトやSNS内で動画コンテンツで表示する広告全般のことを指します。
Youtube広告の場合、広告が再生されるごとに料金が発生する仕組みとなっています。
動画広告は、画像やテキストなどの広告に比べて、一つのコンテンツで伝えられる情報量が圧倒的に多いのが最大の特徴です。
自社のブランドストーリーや商品の使用感など、動画でしか訴求できない情報を入れることで、興味関心の薄い潜在層の目も引きやすくなります。
しかし、動画制作は、画像やテキストのみの広告と比較すると制作するまで時間がかかるため、制作費用が高額になる傾向にあります。
また、視聴者を一定時間拘束する側面があり、コンテンツの質が悪いとユーザーのストレスにつながるため、注意が必要です。
ただ、Web広告のトレンドも、画像やテキストから動画にシフトしつつあるため、コストをかける価値は十分にあるといえます。
メール広告
| メリット | ・急なキャンペーンやお知らせに対応できる ・画像や装飾でよりわかりやすいメールを送れる ・情報に能動的なユーザーにリーチできる ・情報量を多く掲載できる |
| デメリット | ・開封されない可能性がある ・迷惑メールに分類され、そもそも届いていない場合がある ・画像などがうまく表示されないことがある |
| 課金方式 | ・配信課金方式 ・クリック課金方式 |
| ターゲット | 顕在層 |
メール広告とは、メールマガジンの一部に広告を掲載したり、全文が広告の内容で書かれたメールを配信したりするWeb広告のことです。
メールマガジンには、テキスト形式とHTML形式があります。
テキストによって文章のみで訴求する場合は、ほかの広告よりも少ない工数で制作できて急なキャンペーンやお知らせにも対応しやすいのがメリットです。
HTML形式であれば、画像や装飾によって、より多くの情報を盛り込み、視覚に働きかけることも可能です。
メールマガジンを利用するユーザーは、自ら配信を希望していることも多く、情報に対して能動的な傾向があります。
また、すでに商品やサービスを購入したことがある既存顧客に配信する場合は、ニーズが把握しやすいため、ターゲティングがしやすいのもポイントです。
しかし、そもそもメールが開封されなかったり、メール本文の画像や装飾がうまく表示されずイメージダウンにつながったりするなどのデメリットもあるため、注意しましょう。
音声広告
| メリット | ・広告に対する嫌悪感が少ない ・内容を最後まで聞いてもらえる可能性が高い ・詳細なターゲティングができる |
| デメリット | ・音声メディアを利用するユーザー数が少ない ・聞き流されてしまう可能性がある ・配信効果を実感しにくい |
| 課金方式 | 再生回数によって料金が変動 |
| ターゲット | 顕在層と潜在層 |
音声広告とは、インターネットラジオや音楽配信アプリなどで、コンテンツの間に流れるWeb広告のことです。
近年、SpotifyやVoicyといった音声・音楽配信メディアの普及が進んでおり、今後市場が拡大することが予想されます。
音声広告の課金方式は、Youtube広告と同じく、再生回数で料金が発生する仕組みです。
音声・音楽配信メディアのユーザーは、端末を操作せずにコンテンツを聴くことが多いため、広告をスキップされにくいという特徴があります。
また、意外にもユーザーのストレスになりにくく、情報を最後までノンストレスで届けられたり詳細なターゲティングができたりするのも大きなメリットです。
しかし、音声・音楽配信メディア市場自体がまだ成熟しておらず、ほかのWeb広告と比較してユーザー数が少ない傾向にあります。
そのため、効果が得られるかどうか、自社商品やサービスとの相性を精査する必要があります。
リワード広告
| メリット | ・コンバージョンにつながりやすい ・最後まで視聴されやすい ・認知度の向上が期待できる |
| デメリット | ・低評価になりやすい ・広告を閲覧するまで時間がかかるため、ストレスを与える可能性が高い ・動画制作コストがかかる |
| 課金方式 | 決められたコンバージョンの達成率によって異なる |
| ターゲット | 顕在層と潜在層 |
リワード広告とは、広告主が設定したコンバージョンを達成したユーザーに対して、報酬を支払う成果報酬型のWeb広告のことです。
具体的なコンバージョン例としては、動画広告の閲覧やアンケート回答、アプリのインストール、アプリの使用などが挙げられます。
リワード広告は、ユーザーに報酬が入るため、ほかのWeb広告と比較してコンバージョンに達しやすいのがメリットです。
しかし、アプリのダウンロードをコンバージョンに設定した場合には、報酬目的でコンバージョンが達成されることがほとんどです。
そのため、アプリそのものに興味を持たれず低評価になりやすい傾向にあります。
基本的にリワード広告に設定するコンバージョンは手間と時間がかかるケースが多いので、ユーザーがストレスを感じないように工夫することが大切です。
SNS広告
| メリット | ・高精度なターゲティングができる ・ユーザーのストレスになりにくい ・ほかの広告に比べると低コストで運用できる |
| デメリット | ・SNSによって、ターゲットや効果的なアプローチが異なる ・コンテンツの制作に時間がかかる ・炎上する可能性がある |
| 課金方式 | ・クリック課金方式 ・インプレッション課金方式 ・アプリのインストール課金方式 ・動画を再生されるごとに発生する課金方式 ・エンゲージメント課金方式 ・フォロー課金方式 |
| ターゲット | 顕在層と潜在層 |
SNS広告は、TwitterやInstagramなどのSNS上に表示される広告のことで、クリック課金やインプレッション課金、フォロー課金など、さまざまな課金方式があります。
年齢や住んでいる場所など、ユーザー属性を詳細に設定できるため、Web広告のなかでも高精度なターゲティングが可能です。
また、SNSで表示される広告は、通常の投稿に溶け込むように自然に配信されるため、ユーザーのストレスになりにくい点も注目したいポイントといえるでしょう。
ただし、それぞれのSNSによってユーザー層が異なるため、特徴をしっかり把握しておく必要があります。
また、目を引くようなコンテンツを制作しないと、ユーザーから見られない可能性があるので、どうしても手間と時間がかかります。
コンテンツの内容によっては、ユーザーから不快に思われてしまい、炎上する可能性もあるので、十分に気をつけましょう。
インフルエンサー広告
| メリット | ・コンバージョン率が高い ・ターゲティングしやすい ・拡散力が大きい |
| デメリット | ・インフルエンサーの選定が難しい ・依頼料金が高額になる可能性がある ・炎上するリスクがある |
| 課金方式 | 依頼するインフルエンサーによって異なる |
| ターゲット | 顕在層と潜在層 |
インフルエンサー広告とは、SNSで多くのフォロワーを持つインフルエンサーに、自社商材の紹介を依頼する広告手法のことです。
インフルエンサーが持つ影響力は非常に大きく、コンバージョン率が高いのが特徴です。
また、第三者目線でインフルエンサーがレビューをすることによって、フォロワーが自社商材への信用を感じやすい傾向があります。
インフルエンサーが抱えているフォロワーは、性別や年齢層、趣味嗜好といった情報がわかりやすく、ターゲティングがしやすい点も注目すべきポイントです。
そのため、インフルエンサー次第ともいえますが、高額なPR依頼料に見合った成果が得られるケースも少なくありません。
ただ、自社の商材に合ったインフルエンサーの選定が非常に難しく、フォロワーが多いという理由だけで選んでしまうと、思うように成果が得られない場合もあります。
そのため、フォロワーとのコミュニケーションがしっかりと行われているか、過去の投稿内容に違和感はないかなどに着目するのが重要です。
また、依頼したインフルエンサーが不祥事を起こしたことによって、自社が炎上するリスクもあるので、しっかりと検討した上で選びましょう。
どのWeb広告を導入すべき?自社に合わせた選び方

ここまでの解説で、多種多様なWeb広告についての特徴が把握できたのではないでしょうか。
自社の施策にWeb広告を導入すると決まれば、次に考えるべきは「自社に合うWeb広告の選定」です。
実際にWeb広告を選ぶ際には、以下4つのポイントを意識しましょう。
- Web広告を導入する目的で選ぶ
- ターゲット層や自社商材との相性で選ぶ
- 費用対効果を意識して選ぶ
- 自社の予算に合わせて選ぶ
順番に解説します。
Web広告を導入する目的で選ぶ
集客施策に効果的なWeb広告やリピーター獲得施策に効果的なWeb広告など、さまざまな種類がありますが、それぞれ役割が異なります。
そのため、まずは「新規顧客を獲得したい」「リピーターを増やしたい」「ブランド力を認知させたい」といった、自社の目的を明確にしてみましょう。
例えば、新規顧客の獲得が目的であれば、潜在層や顕在層に効果的なSNS広告やディスプレイ広告、リスティング広告がおすすめです。
また、リピーター獲得ならメール広告やリターゲティング広告、ブランド力アピールなら純広告や記事広告といったWeb広告を選ぶとよいでしょう。
自社のマーケティングですでに成果がある施策と、弱みになっている施策を可視化することで、Web広告を導入すべき施策が把握できます。
ターゲット層や自社商材との相性で選ぶ
自社商材とWeb広告との相性は、「ターゲット層」と「訴求するコンテンツの形式」で見極められます。
そのため、まずは自社商材のターゲット層を明確にしてみましょう。
SNS広告を例に挙げると、20〜30代の若い女性であればInstagram広告、40〜50代の中年男性であればFacebook広告がターゲットに合うWeb広告といえます。
また、画像・テキスト・動画・音声など、どのコンテンツ形式で訴求するかを精査するのも重要な要素の一つです。
例えば、商品の使用感やブランドストーリーといった、情報量の多いコンテンツを短い時間で訴求するのであれば、動画広告がおすすめです。
また、購入に至るまでに自社商材に関連する情報を提供して顧客を育成する必要があれば、リスティング広告を選ぶとよいでしょう。
このように、ターゲット層とコンテンツ形式を基準として、相性のよいWeb広告を絞り込んでいきましょう。
費用対効果を意識して選ぶ
Web広告を選ぶ基準として、予算の範囲でどれくらいの効果が得られるかどうかを精査するのも重要なポイントです。
そのため、単純に単価の安いWeb広告だけに絞ればいいというわけではありません。
費用対効果を高めるWeb広告の運用で、意識するのは以下の3つです。
- 配信回数や配信ごとの単価
- ターゲット層
- クリエイティブ制作の工数や費用
例えば、クリック単価の低いSNS広告の割合を増やして、リスティング広告では競合の少ないニッチなキーワードに絞って出稿する方法はいかがでしょう。
SNS広告で認知を促して潜在層の母数を担保しながら、成果率の高いリスティング広告を運用することで、顕在層を獲得できるだけでなく、コストも抑えられます。
このように、Web広告同士の相性も考慮した上で戦略的に組み合わせる方法もおすすめです。
自社の予算に合わせて選ぶ
Web広告によって課金方式や費用が異なるので、自社の予算に合わせて選ぶ方法もあります。
例えば、予算が少なくて少額からWeb広告運用を行いたい場合は、リスティング広告やSNS広告などがおすすめです。
逆に十分な予算を確保できる場合は、純広告やインフルエンサー広告なども候補に入るでしょう。
ただし、予算が確保できてもWeb広告におけるノウハウがなければうまくいきません。
そのため、まずはそれぞれのWeb広告の特徴を理解するようにしましょう。
「自社の予算に合わせたWeb広告の選定方法がわからない」「Web広告のインハウス運用に課題を感じている」などの悩みを抱えている方は、Web広告特化型のWebマーケティングスクール「デジプロ」で、実践型の広告運用を学んでみませんか?
Web広告導入のメリット

予算が限られている企業でも参入しやすいWeb広告ですが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、Web広告導入のメリットとして、以下の5つを解説します。
- 少額で出稿できる
- 精緻なターゲティングが可能
- マス広告と比較し効果測定も容易
- 費用さえかければ短期間での集客効果も期待
- マス広告と違いいつでも広告出稿を停止できる
それぞれ詳しく掘り下げるので、参考にしてみてください。
小額で出稿できる
Web広告は、広告出稿費用の上限をあらかじめ設定しておけるため、出稿コストの自由度が高いのが特徴です。
そのため、必ずしも数百万円規模の予算がないと運用できないわけではありません。
なかには、数万円規模の予算でスモールスタートからWeb広告運用に参入する企業も数多くあります。
クリック課金方式や成果報酬型が採用されているWeb広告もあるため、費用対効果の高い運用が可能です。
また、広告枠を獲得できる評価基準として、出稿額だけでなくリスティング広告のように品質が加味される仕組みのWeb広告も存在します。
運用次第で予算を大幅に抑えられるため、どのような企業にとってもハードルが低いといえるでしょう。
精緻なターゲティングが可能
Web広告では、Cookieによって精微なターゲティングが可能です。
Cookieとは、インターネットやアプリを使用するユーザーのさまざまな情報をWebブラウザに保存する仕組みのことです。
マーケティング集客において、自社商品やサービスの情報を狙ったターゲットに届けるのは、もっとも重要なポイントといえます。
ターゲティングの正確さによって集客効果は大きく変わるため、Web広告は従来のマス広告よりも、コンバージョンが達成しやすい傾向にあるのです。
マス広告と比較し効果測定も容易
Web広告では、ユーザーのアクセス数が多い広告やコンバージョン率の高い広告ページなど、ユーザーの行動を全て数値に表して分析できます。
広告出稿後の顧客反応がわかりにくいマス広告とは大きく異なるポイントです。
正確な効果測定ができるため、Web広告運用をより効果的に改善することが可能です。
費用さえかければ短期間での集客効果も期待
Web広告はコストを抑えながら運用できるのも魅力の一つですが、しっかりと予算を投入すれば、短期間での集客にも期待ができます。
なぜなら、費用をかけて広告配信の回数を多く設定すれば、その瞬間からより多くのユーザーに広告を表示できるからです。
広告を閲覧するユーザーの母数が多ければ、コンバージョン数も比例して増加するのはいうまでもありません。
そのため、予算がしっかり確保できて短期間での集客を行いたいケースでも、Web広告なら柔軟に対応可能です。
マス広告と違いいつでも広告出稿を停止できる
マス広告は、あらかじめ出稿期間が決まっており、途中で出稿を停止するのは容易ではありません。
一方、Web広告は出稿主のタイミングで自由に出稿期間を設定できます。
WebマーケティングはWeb広告運用以外にも、SEO対策やSNS運用など、ほかの施策も並行して進める企業が多く見受けられます。
そのため、ほかの施策で成果が表れたら出稿期間中であっても、Web広告のコストを削減したいというシーンが出てくるかもしれません。
そのような場合でも、Web広告であればいつでも出稿を停止できるため、柔軟性に優れているといえるでしょう。
Web広告導入のデメリット
Web広告を効果的に運用するためには、以下のデメリットについてもしっかりと把握しておく必要があります。
- Web広告プロダクトを理解しないと期待する効果が得られない
- 競合が多いキーワードは単価が高騰しやすい
- ABテストなど効果検証を継続する必要がある
それぞれ詳しく解説します。
Web広告プロダクトを理解しないと期待する効果が得られない
Web広告には、リスティング広告やSNS広告など、さまざまなWeb広告プロダクトが存在します。
Web広告プロダクトごとにユーザー層や効果に違いがあるため、しっかり理解していないと、期待する効果が得られない可能性があります。
そのため、「とりあえず多くのWeb広告プロダクトに出稿してみよう」「出稿費用の安いWeb広告プロダクトだけに出稿しよう」といった考え方はやめましょう。
自社商品やサービスに適したWeb広告プロダクトを選定しないと、満足のいくコンバージョンが得られず、逆にコストがかさんでしまう原因になりかねません。
Web広告運用をスタートする際は、あらかじめWeb広告についての知識を習得しておくことをおすすめします。
競合が多いキーワードは単価が高騰しやすい
特にリスティング広告にあてはまるデメリットですが、競合が多いキーワードは、クリック単価が高騰しやすい傾向にあります。
なぜなら、検索回数の多いキーワードはユーザーの母数が多いため、集客効果が得やすい分、競合の広告主も比例して増加する傾向にあるからです。
そのため、競合の少ないキーワードにも並行して出稿したり、より高品質なページを制作して広告スコアを上げたりするなど、戦略的に運用することを心がけましょう。
ABテストなど効果検証を継続する必要がある
Web広告運用は、出稿までの過程にほとんどの工数が詰まっているマス広告とは異なり、出稿してからの効果検証が勝負といっても過言ではありません。
効果検証の例として、いくつかのパターンに分けて広告ページを複数制作し、よりコンバージョン率・クリック率の高いページを検証する「ABテスト」が挙げられます。
Web広告運用はSEO対策やSNS運用といった長期的な施策と比べて、短期的に効果を得られるのが強みです。
しかし、出稿後の効果検証を繰り返して改善策を実行し続けるためには、相応の手間とリソースが必要となります。
そのため、出稿後の効果検証を見据えた上で万全な運用体制を整えておきましょう。
Web広告運用を成功させるために意識すべき3つのポイント
Web広告運用を成功させるために意識すべきポイントは、以下の3つです。
- ユーザーニーズをしっかり意識する
- ツールの機能や使い方を把握する
- PDCAを回す
それぞれ詳しく解説します。
ユーザーニーズをしっかり意識する
自社の好みだけでWeb広告を運用しても、成果に結びつきません。
Web広告運用を成功させるには、ユーザーニーズを意識することが大切です。
そのため、まずは顕在層からアプローチしてみましょう。
顕在層であれば、すでに商品やサービスを認知しており、購入する可能性が高い状態にあるため、Web広告を運用することですぐに売り上げにつながりやすい傾向にあります。
ユーザーニーズを意識したWeb広告運用を行うには、ペルソナを明確にすることが重要です。
ユーザーがどのような行動を取るのかを意識した上で、運用するWeb広告を選びましょう。
ツールの機能や使い方を把握する
Web広告運用では、ヒートマップツールやデータ分析ツールなど、さまざまなツールを活用することで業務の効率化につながったり、改善点の発見に役立ったりします。
しかし、便利なツールを導入しても、機能や使い方を理解していなければ、それぞれのWeb広告の特徴を活かせません。
そのため、各ツールがWeb広告運用のどの場面で必要なのかを確認し、必要なツールをピックアップした上で使い方を把握しましょう。
PDCAを回す
Web広告運用の仕事は、Web広告を掲載して終わりではありません。
掲載後にはデータ分析を行い、改善点を洗い出して改善案を実行します。
このように定期的にPDCAを回すことで、それぞれのWeb広告における効果を最大化できます。
PDCAを回すときも、正確なユーザーニーズの把握や各広告手法の理解が欠かせません。
どのWeb広告を運用すればいいか悩んでいるのであれば「デジプロ」
どのWeb広告を運用すればいいか悩んでいるのであれば「デジプロ」がおすすめです。
デジプロは、Web広告運用に特化したWebマーケティングスクールです。
個人向けだけでなく、企業のWeb広告運用におけるインハウス化もサポートしており、多くの卒業生がWeb広告運用の担当者として成果を挙げています。
デジプロの特徴を5つ紹介します。
主要なWeb広告プロダクトを網羅
デジプロでは、多様なWeb広告プロダクトを網羅し、実践の運用まで学べるのが最大の特長です。
具体的には、以下のようなWeb広告プロダクトを学習します。
- リスティング広告
- Google 広告
- Yahoo!広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- ディスプレイ広告
はじめにWeb広告の基礎を固め、各種プロダクト運用への応用知識をインプットし、実際に広告運用を体験してアウトプットできるカリキュラムがデジプロの魅力です。
Web広告運用において、知識はもちろん、実践経験が何よりも重要な仕事です。
自社でWeb広告運用を本格的に導入する前に、実践を経た即戦力人材を育成できていれば、より短期間で成果を得られます。
講師は現役トップマーケターで構成
デジプロに在籍する講師は、GMOグループやサイバーエージェントなど、業界最大手のWeb広告企業で活躍してきた現役マーケターです。
Web広告運用で多くのクライアントの利益を向上させてきたトップ講師が、貴社の広告運用インハウス化を徹底サポートします。
また、生徒一人ひとりをサポートするパーソナルトレーナーになってくれるのもデジプロの強みです。
独立やキャリアについても相談できるので、将来に対する不安や悩みを抱えているのであれば、一度話を聞いてもらいましょう。
全国8ヵ所で通学授業にも対応(順次拡大中)
デジプロでは、通学授業に対応している教室が全国8ヵ所にあります。
- 東京
- 大阪
- 福岡
- 千葉
- 大宮
- 横浜
- 広島
- 名古屋
Webマーケティングスクールはデジプロ以外にもありますが、ほとんどはパソコン一つで行うオンライン授業です。
オンライン授業は、時間や場所に縛られず自由に講義を受けられるメリットがあります。
しかし、疑問点をその場で解決できなかったりモチベーションの維持が難しかったりといったデメリットもあります。
デジプロは教室に通い対面で授業を受けると、モチベーションを維持したまま効率的な学習が可能です。
教室に近い場所で働いている方であれば、本業が終わってからでも通えます。
インハウス運用実績も豊富
デジプロでは、卒業後にインハウス運用を成功させた生徒を多数輩出しています。
マーケティング担当者や経営者など、多くの卒業生から、自社のマーケティング戦略を改善できたとの声を数多くいただいています。
インハウス運用でデジプロを受講した卒業生へのインタビューは、こちらをご覧ください。
>> 広告のインハウス運用で悩んでいる方は受講してほしい。「やっているだけ」から「成果の出せる」広告運用になるまで。
>> 経営者は全員デジプロを受講した方がいい!コンサルを受けると思えば確実に元が取れる
充実した転職サポート
デジプロの転職コースでは、Webマーケティング未経験者でも転職できるように、さまざまなサポートを用意しています。
具体的なサポート内容は、以下の通りです。
- キャリアカウンセラーによる個別サポート
- マーケティング・クリエイティブ専門の人材エージェントである「マスメディアン」からの求人紹介
- 卒業時に修了証明となるオープンバッジ
- 資格補助制度
- 担当講師による推薦状の作成
- ポートフォリオの作成
- 書類添削
- 面接対策 など
さらに詳しく知りたい方は、「転職サポート」をご覧ください。
即戦力として活躍できる人材を育成することに自信を持っているデジプロだからこそ、充実した転職サポートが受けられます。